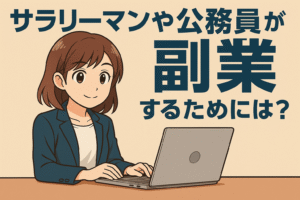宗教系の学校に通っていたことの効用
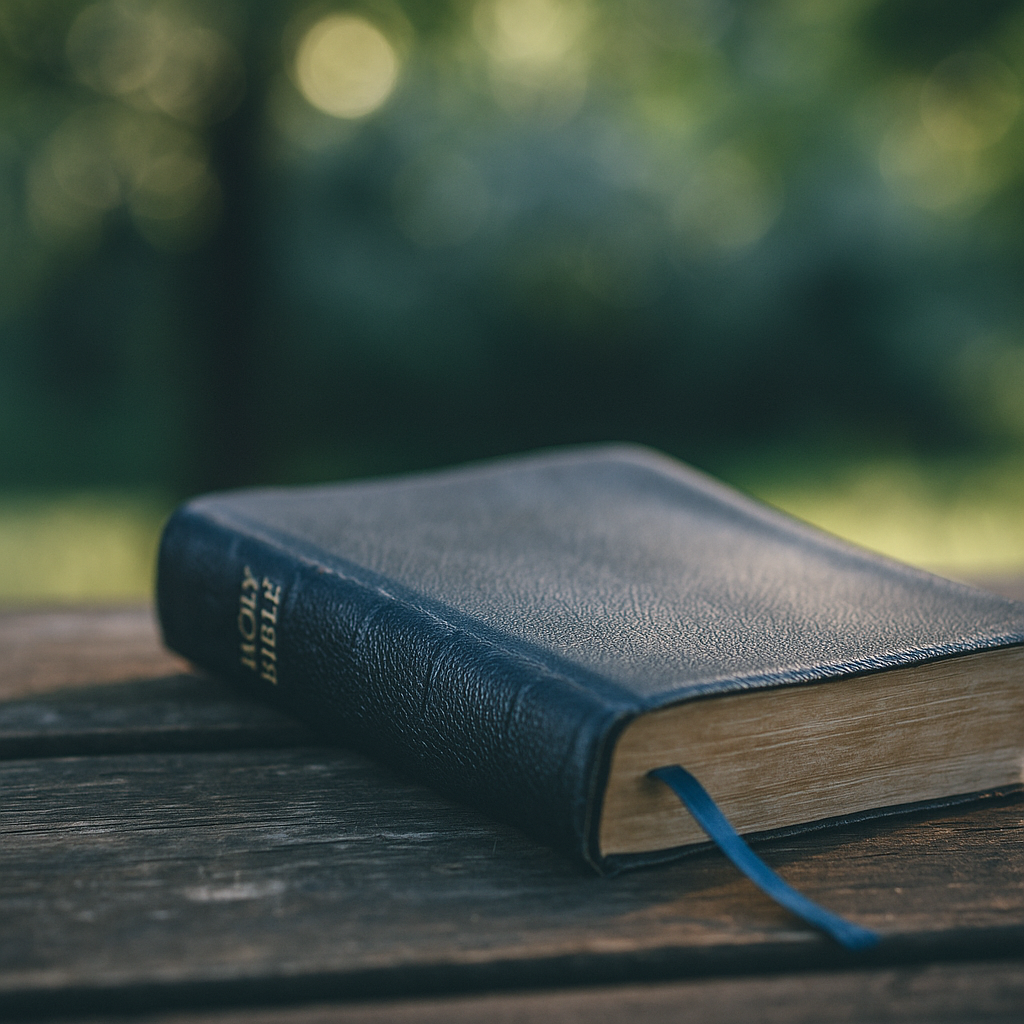
中学はキリスト教系の学校でした。といっても、家族を含めて信者ではありません。多くの卒業生がそうだと思います。
昼休みになると講堂に集まり、讃美歌を歌い、聖書の一節を朗読する。そういう日常がごく当たり前のようにありました。
ただし、当時も今もキリスト教の教義そのものにはほとんど興味がありませんでした。むしろ、聖書の中にたまに登場するちょっとエロいワードを友達と見つけあっては、どっちがより破廉恥な箇所を発見できたかを競い合っていました。
陰キャらしいしょうもない遊びです。
高校時代、「神は死んだ」で炎上
ちなみに高校もキリスト教系でした。今でも印象に残っているのが、「倫理」の授業でニーチェの有名な言葉「神は死んだ」という一節を扱ったときのことです。
その日の授業が終わったあと、日直が黒板を消し忘れたんですが、次の時間がよりによって「聖書」。
しかも担当は、ちょっと宗教過激派(失礼)の先生でした。
教室に入ってきた瞬間、黒板の「神は死んだ」を見て、ブチギレはじめました。
こんな漫画みたいな出来事あるか?と思いますが、実際にあったのでしょうがないです。
神的な概念の内在化
今も昔も私は神は存在しないと思っています。
でも同時に、“神的な要素”を自分の中に内在化させることは矛盾していないとも思っています。
つまり、神という存在を「信じる対象」ではなく、「行動を律する基準」として置いておく感じですかね。
「思考は現実化する」という有名な本がありますが、あれも宗教的な構造をしていると思います。
毎日決まった時間に起きて、やるべきことをやり、なりたい自分に近づく努力をする。
これって、言い換えれば現代の修道生活みたいなものです。
一種の宗教。でも、努力の方向としては筋が悪くない宗教です。
思考が現実になるという仮説
人間の思考は、けっこうな確率で現実を形作ると思っています。
「どうせ自分なんて」と思って生きていると、たいていその通りの現実になります。
カイジの大槻も言っていましたが、「今日をがんばった者のみ明日が来る」的に何かを積み重ねていくと、未来が変わるかもしれません。
自分の不遇を嘆いていても、その思考が現実を貧しくしていく。
努力を避ける理由を「どうせ」で片づけてしまえば、そこに残るのは「どうせ」の人生かもしれません。
信仰とは、神を信じることではなく、自分の中に信じる対象を住まわせることなのかもしれません。
それが「神」という名前であれ、「理想の自分」という名前であれ、この際どちらでもいいと思います。
っということを図書館で見つけたナポレオン・ヒルの『思考は現実化する』を見つけてふと思いました。
読書の秋ということで、本を沢山読もうと思います。