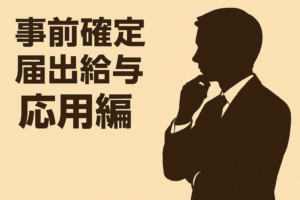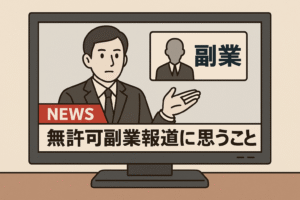新NISAの非課税メリットと、税務署職員が意外と使っていない理由
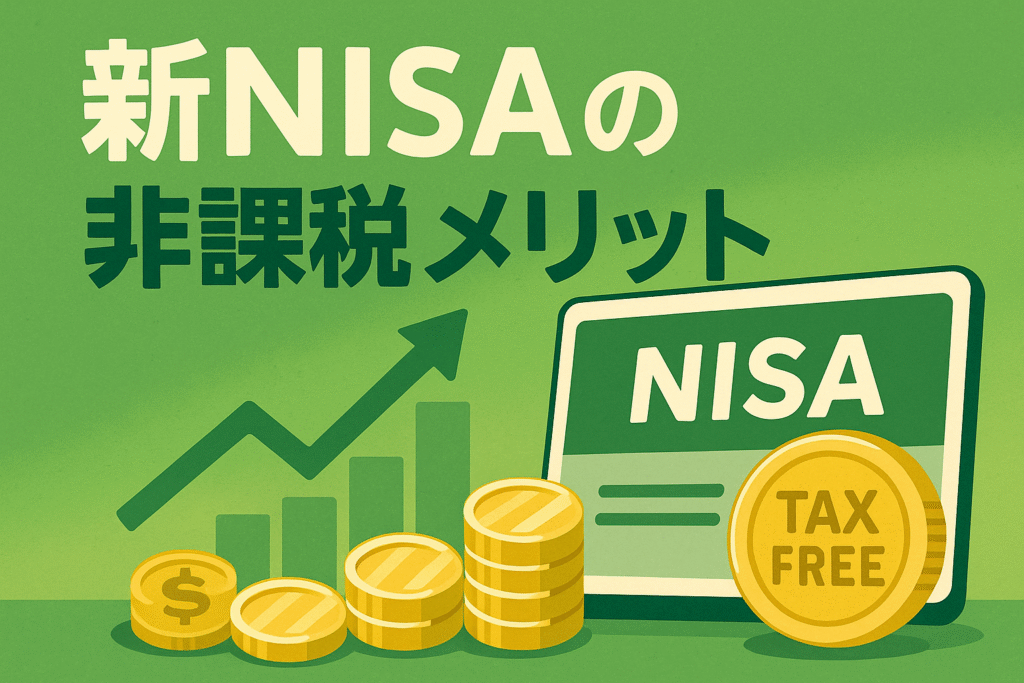
2024年から「新NISA(少額投資非課税制度)」が始まりました。
従来のつみたてNISA・一般NISAが一本化され、恒久化された制度です。
非課税枠が大幅に拡充されたこともあり、投資初心者にとっても利用しやすくなりました。
私は旧つみたてNISA時代から引き続きNISAを活用しています。
ただ、意外に思われるかもしれませんが、税務署の職員が皆NISAを使っているわけではありません。
目次
現職時代の実感:「NISAやってない人、けっこう多い」
現職時代の飲み会で投資の話題になると、
「NISAもふるさと納税もやっていない」という職員が少なくありませんでした。
ふるさと納税については、「地方税財源の移転」という思想的な理由から
あえて利用しないという考え方も理解できます。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)は、所得控除が取れるとはいえ、
60歳まで資金が拘束される点を嫌う人も多いでしょう。
しかし、NISAまでやっていない職員が多かったのは正直意外でした。
税の仕組みを熟知している立場だからこそ、
制度の有利さは理解しているはずなのですが……。
公務員にとっての「NISAの心理的ハードル」
一つの要因は、倫理面の慎重さだと思います。
実際、勤務時間中に株取引を行って懲戒処分となったニュースを
見たことがある方も多いでしょう。
また、国税職員の場合、直近1年間に所属していた部署の所掌法人の株式は
取引が禁止されています。
(株式取引が「利害関係」に当たると判断されるためです。)
そのため、「少しでも怪しく見える行動は避けよう」という
心理的ブレーキが働くのかもしれません。
もっとも、指数連動型の投資信託(いわゆるインデックスファンド)への投資は問題ありません。
NISA口座を通じて、S&P500やオルカンなどのファンドに積み立てる分には
倫理上の問題はないとされています。
新NISAの非課税メリット
NISAの最大の特徴は、配当・譲渡益が非課税になることです。
通常、課税口座で株や投資信託を売却すると、
利益に対して20.315%(所得税+住民税)が課税されます。
しかし、NISA口座内で得た利益は、非課税。
確定申告も不要です。
たとえば、100万円の利益を確定させた場合、
課税口座なら約80万円のキャッシュが残り、約20万円の税金が天引きされますが、
NISAならそのまま100万円のキャッシュが残ります。
所得税法上の注意点:損益通算できない
NISAのもう一つの特徴として、損益通算ができない点があります。
通常の課税口座では、A銘柄の利益とB銘柄の損失を相殺(損益通算)できますが、
NISA口座の損失は相殺できません。まぁ売却益非課税との整合性から仕方ないですね。
如才無きことながら、これらの点を理解していただいて、積極的に活用していきたいです。
制度が続くことを願う
非課税の恩恵は非常に大きいですが、
恒久措置であるとはいえ、将来の制度改正リスクもゼロではありません。
たとえば、
- 恒久措置の撤回
- 売却益への社会保険料負担の導入
- 投資額上限の縮小
といった議論が将来出てくる可能性もあります。
長期で安心して投資を続けられるよう、
制度が安定して運用されることを願うばかりです。
まとめ:制度を理解し、安心して使う
NISAは、税制の中でもっともシンプルかつ強力な「合法的な非課税枠」です。
制度を正しく理解し、ルールの範囲内で活用すれば、
誰でも再現性のある資産形成が可能です。
税務署職員であれ、独立した税理士であれ、
自分の手で制度を使いこなしてこそ、説得力のある助言ができます。
制度があるうちに、ぜひ味方につけていきましょう。