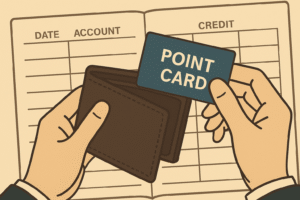税務署職員の“無許可副業”報道に思うこと
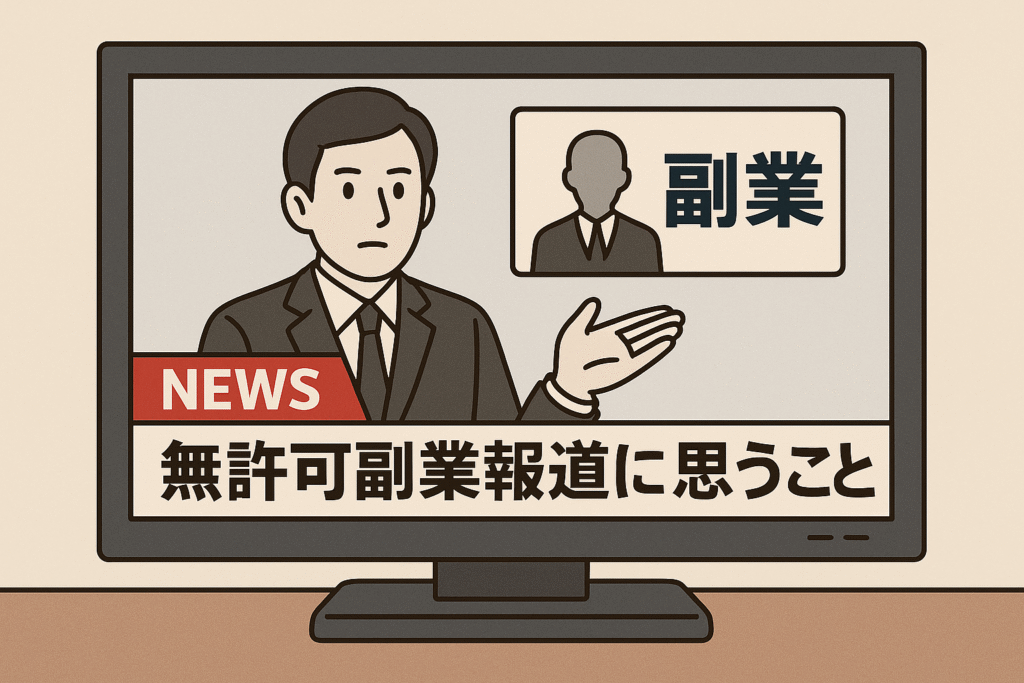
先日報道された「東京国税局職員の無許可副業による懲戒免職処分」。
税務行政に携わる立場として、残念なニュースでした。
公務員の副業に関しては制度上の制限があるものの、
「どこまでが許され、どこからが違反になるのか」
このニュースをきっかけに改めて考えてみたいと思います。
事件の概要:許可なく副業、さらに申告漏れ
報道によると、都内の税務署に勤務していた50代の女性職員は、
2017年から2023年までの約6年間、国税局の許可を得ずに
撮影エキストラやイベントスタッフとして計219回働き、
報酬・給与として222万円を受け取っていました。
問題はそれだけではありません。
得た収入について税務申告をしていなかったのです。
さらに調査の結果、
- 納税者情報を31回私的に検索
- 文書を無許可で庁外に持ち出し
- 勤務時間中に77回の株取引
といった行為も確認されました。
東京国税局は職員に対し税務調査を実施し、
重加算税を含む約33万円を追徴課税。
懲戒免職処分としました。
なぜ発覚したのか
詳細な端緒は報じられていませんが、
おそらく内部通報や勤務状況の異変がきっかけだったと考えられます。
「副業している」ことをベラベラ喋ったり、「離席が多く、この職員は何しているんだろう」など、
何らかの形で周囲に気づかれるケースが多いのが実情です。
税務署内部では、こうした不正事案の発覚は往々にして内部告発が端緒になっているような気がします。
倫理よりも「管理体制の脆さ」に注目すべき
今回の処分理由には、副業以外にも
「文書の無許可持ち出し」「勤務中の株取引」が含まれています。
職員本人の倫理意識の欠如は明白ですが、
同時に、組織内部の管理体制にも疑問が残ります。
特に「勤務時間中の株取引77回」という点。
別件逮捕のように、こういう明白な違反からヒアリングを重ねて、
本件の事件も発覚したのかもしれませんね。
国税当局は「信頼を損ねた」とコメントしましたが、
個人の逸脱行為を防げなかった組織体制面の反省も言及すべきだったのかと思います。
「お金のためではなく撮影を見たかった」
報道によれば、本人は
「収入を得たかったわけではなく撮影を見たかった」と話しています。
動機はやや不可解ですが、
もし“好きなことをやりたかった”という自己実現的な動機であれば、
なおさら組織内での相談をはじめ、未然に防げたような気がします。
副業の是非以前に、
組織と個人の間にあるコミュニケーションの断絶を感じます。
税理士として思うこと
このような報道が出ると、
「税務署員が税金を申告していなかった」と強い印象を与えます。
税務行政の信頼を揺るがす行為であることは間違いありません。
しかし、制度的な観点で見れば、
副業禁止というルールが現在の働き方に合っていない面もあります。
副業・兼業を通じて得られるスキルや経験が、
むしろ本業の公共サービス向上につながることもあります。
一律禁止ではなく、
「申請・許可制の透明な運用」へと時代に合わせた見直しが必要でしょう。
まとめ
今回の件は、個人のモラルの問題であると同時に、
組織文化や管理体制の課題でもあります。
国税の仕事は信頼があってこそ成り立ちます。
だからこそ、現職の方々には
「職員一人の行動が全体の信用を左右する」という自覚を持ってほしいと思います。