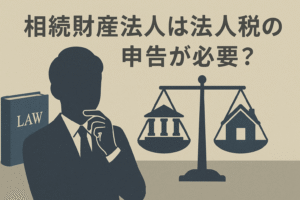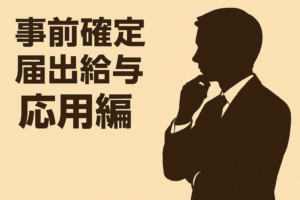事前確定届出給与:基本編
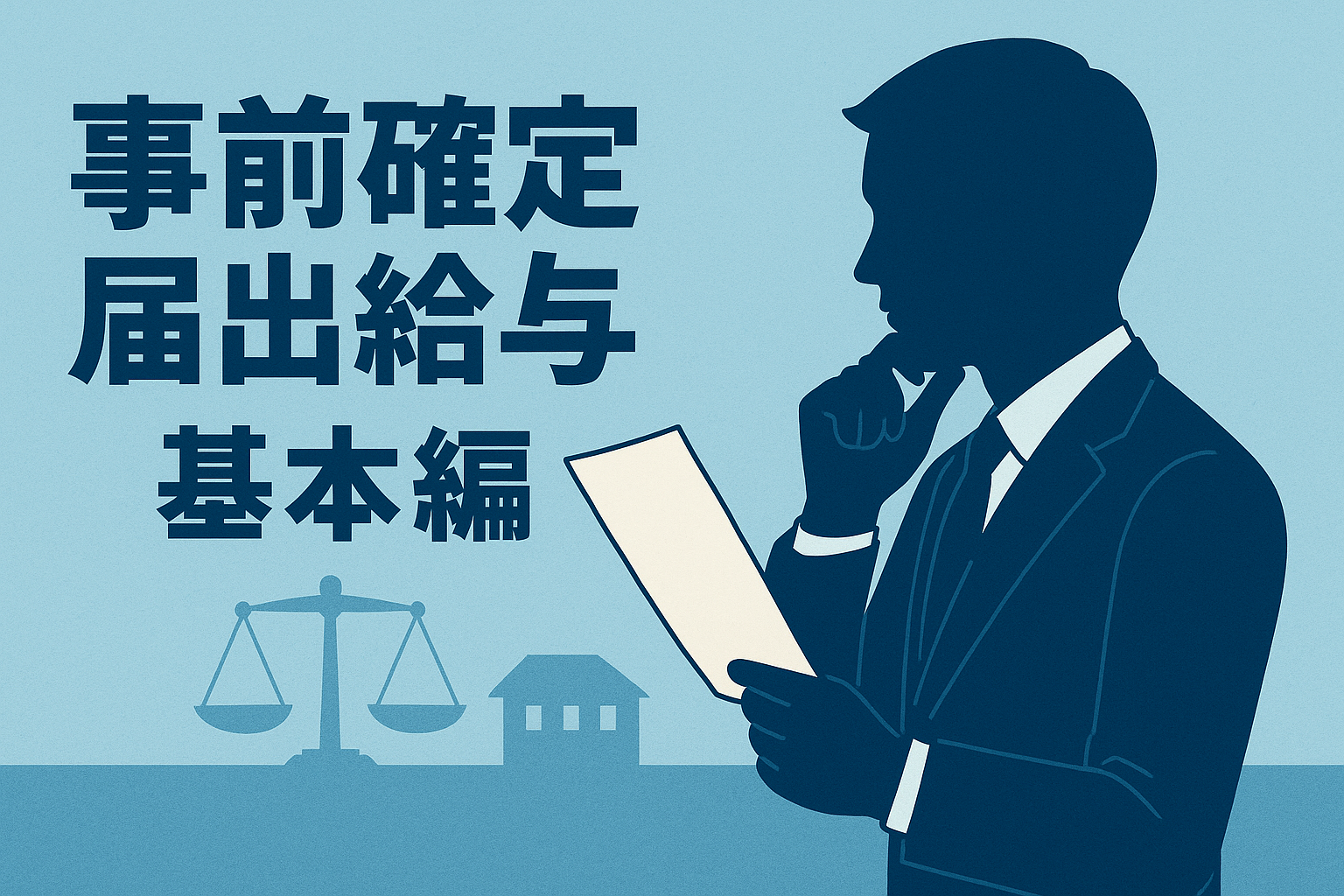
「事前確定届出給与を活用すると、社会保険料を減らせる」と耳にしたことはありませんか。
今回はこの制度の仕組み・効果・リスクを、税理士としての視点から整理します。
どのような理屈で社会保険料の削減につながるのか。実務上のリスクや誤解されやすい点も含め、基本的な内容を解説します。
目次
1. 事前確定届出給与とは?
「事前確定届出給与」とは、役員に支給する賞与(ボーナス)を、事前に税務署へ届け出た上で支払う制度です。
国税庁の定めにより、
- 「支給予定日」
- 「支給対象者」
- 「支給金額」
を記載した「事前確定届出給与に関する届出書」を、原則として株主総会決議の日から1か月以内または事業年度開始の日から4か月以内に提出します。
(提出先は所轄税務署長です。)
通常、役員報酬は毎月同額でなければ損金算入(経費扱い)できません。
しかし、この制度を使うことで、あらかじめ届け出た金額と支給日に限り、ボーナスを損金算入できるという仕組みです。
2. 年収800万円でも社会保険料が半分になる理由
この制度を活用すると、報酬の分け方によって社会保険料の負担を抑えることができます。
ケース1:通常の報酬設定
- 月給:66万円(年収800万円)
- 社会保険料:約120万円
ケース2:事前確定届出給与を活用
- 月給:5万円
- ボーナス(届出済み):740万円
- 社会保険料:約60万円(試算)
年収は同じ800万円でも、保険料は約半分。
この差は、社会保険料の「標準報酬月額」と「標準賞与額」に上限があることに起因します。
健康保険には、1年度(4月〜翌年3月)の賞与額に対して累計573万円までという上限があり、厚生年金には1回の賞与につき150万円という上限があります。
この上限を超えた部分には保険料がかかりません。
そのため、賞与を高額に設定すると、上限を超えた部分が保険料計算の対象外となり、結果的に負担が軽くなるのです。
3. 高額療養費制度でも“低所得者扱い”になる理由
さらに、この設定には思わぬ副次効果があります。
「高額療養費制度」では、医療費の自己負担限度額を算定する際、基準となるのは標準報酬月額(=月給部分)です。
賞与額は計算に含まれません。
したがって、月給を極端に低く設定していると、医療制度上は「低所得者」として扱われる場合があります。
たとえば、
- 年収800万円
- 月給5万円、賞与740万円
このような設定をした場合、医療費の自己負担上限は月57,600円程度となり、年収370万円以下の人と同等の水準になります。
つまり、社会保険料を減らしつつ、公的医療制度上の保障を維持できるという点で、非常に強力な効果を持つ制度です。
4. 実行前に知っておくべき5つのデメリット
この制度は非常に有効ですが、実行には注意が必要です。
以下の5点は、制度を正しく運用するための重要な留意事項です。
(1)届出内容のズレが命取りになる
届出書に記載した「支給日・金額」と、実際の支給が1日でも、1円でもズレると、ボーナス全額が損金不算入になります。
たとえば、届出が30万円で実支給が50万円なら、差額の20万円だけでなく、50万円全額が経費になりません。
この損金不算入は翌期以降に取り戻すことができず、永久に損金算入できない扱いとなります。
(2)会社業績の悪化による赤字リスク
支給額は事業年度開始時点で確定するため、途中で減額できません。
売上が想定より伸びなかった場合、支給負担が原因で赤字になる可能性があります。
ネット上では「支給日前に不支給決議をすれば問題ない」といった説明をよく見かけます。
たしかに、“支給していないのだから損金算入もされていない、よって税務上の否認対象も存在しない”という理屈は、一見筋が通っているように見えます。
しかし、会社法や民法の一般的な理解では、支給決議をもって報酬債務はすでに成立しており、これを後から不支給決議によって取り消す行為は「債務の消滅」にあたると解されます。つまり、形式的に支給していないとしても、報酬債務を免除(あるいは放棄)したという事実が残るのです。
この場合、税務上は「債務消滅益」が論点となり、「支給しなかったからセーフ」という単純な話ではありません。
(3)生活費の確保が課題
月給を下げるため、支給までの生活費を自分で賄う必要があります。
会社からの一時的な貸付で補う方法が紹介されることもありますが、返済の実態や資金繰りの整合性が取れない場合、税務上「役員賞与の前渡し」とみなされるリスクがあります。
(4)公的保障の減少
厚生年金・傷病手当金・出産手当金などの給付額は月給ベースで算定されます。
したがって、将来の年金額や保障額は減少します。
(5)退職金の節税効果が下がる
役員退職金の適正額は「最終月給×在任年数×功績倍率」で算定するのが一般的です。
月給を下げすぎると、将来的に退職金の非課税枠や節税効果が小さくなる点も見逃せません。
5. まとめ:知識を武器に、制度を味方につける
「事前確定届出給与」は、正しく活用すれば経営者のキャッシュフロー改善に役立つ制度です。
一方で、税務署への届出・社会保険・生活資金の3つを同時にコントロールする必要があり、専門知識が不可欠です。
制度上の“抜け道”のように見える部分も、あくまで法令に基づいた正式な制度です。
ただし、今後の税制改正で見直される可能性もあるため、常に最新の法令・通達に注意する必要があります。
税理士として、制度の“抜け道”を推奨する意図はありません。
ただし、制度として正式に認められている以上、法令を正しく理解し、改正に柔軟に対応する姿勢が重要です。
活用を検討する場合は、税理士などの専門家と二人三脚で設計することをおすすめします。
経営者が制度を「知っているかどうか」で、将来の資産形成は大きく変わります。
まずは自社の財務状況と生活設計を見直し、制度を味方につける視点を持つことが、長期的な安定経営への第一歩です。