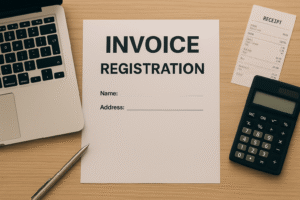もし親が認知症になったら、銀行口座はどうなる?
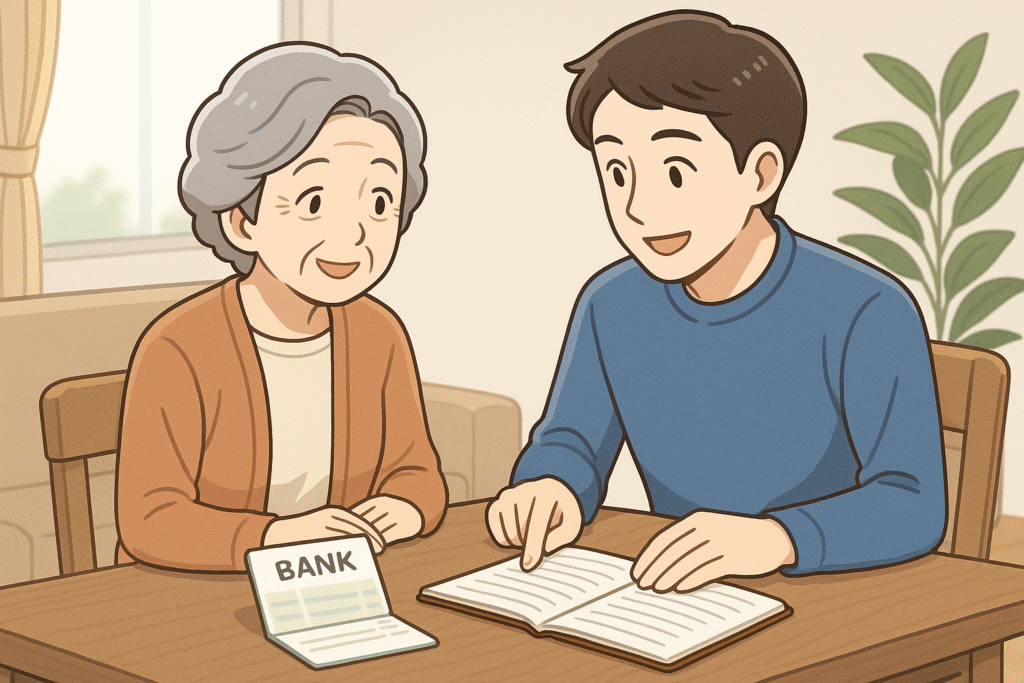
― 現実的でやさしい備え方 ―
「もし親が認知症になったら、銀行口座はどうなるんだろう…」
そんな不安を感じたことはありませんか?
親の判断能力が低下すると、銀行は詐欺防止や相続トラブル防止のため、口座を凍結します。
そうなると、たとえ家族であってもお金を引き出すことはできません。
この記事では、突然の口座凍結に備えるための現実的な対策を紹介します。
いますぐ始められるシンプルな方法から、法的にしっかりした制度まで。
ご家庭に合った選択肢を見つけるきっかけになれば幸いです。
目次
「親のキャッシュカード」を使う方法
まず紹介したいのは、「子どもが親のキャッシュカードを使って預金を引き出す」こと。
もちろん、無断で使えば違法です。
しかし、親本人の明確な承諾があり、生活費や介護費のために使う場合は、実務上問題ありません。
ポイントは、親が元気なうちに「暗証番号」「保管場所」を共有し、
そのうえで使用目的と使途管理のルールを明確にしておくことです。
ただし、注意点もあります。
- 親が認知症になった後ではカードの再発行がほぼ不可能
- 他の家族の同意がないまま使うと、のちに「使途不明金」と疑われるリスク
この方法を選ぶなら、1円単位で支出を記録し、領収書をすべて保存。
透明性を保つことがトラブル防止の鍵です。
私自身も税理士として、実家のこの管理をどう引き受けるか、少しずつ準備しているところです。
後ろめたさゼロの「代理人制度」
「親のカードを預かるのは気が引ける」という方には、金融機関の代理人制度がおすすめです。
これは預金者本人が元気なうちに代理人を登録し、銀行での手続きを代行できる制度です。
たとえば三井住友銀行では、代理人専用のキャッシュカードを発行しており、
本人が外出困難になった場合でも、代理人が入出金や支払いを行えます。
代理人制度には2タイプあります。
- 速攻型:親が元気なうちから使えるタイプ
- 予約型:判断能力低下後に医師の診断書などで発動するタイプ
また、銀行だけでなく証券会社にも代理人制度があります。
親の投資資産を安全に管理する手段としても有効です。
最もシンプルで効果的な「口座の集約」
意外と見落とされがちなのが、口座の集約です。
多くの家庭で、
- 年金の振込口座
- 貯蓄専用口座
- 公共料金の引落し口座
…など複数の銀行を使い分けています。
この状態で主要口座が凍結されると、自動引落しが止まり、生活費が滞るリスクがあります。
年金の受取口座と支払い口座を一つにまとめておくことで、
凍結後も自動入金・引落しが継続するケースが多く、非常に有効です。
不動産や資産がある家庭に「家族信託」という選択肢
資産規模が大きい家庭では、より包括的な仕組みも検討すべきです。
注目されているのが「家族信託」です。
家族信託は、
- 本人が元気なうちの資産管理(委任)
- 判断能力が低下した後の管理(後見)
- 死後の承継(遺言)
をひとつの契約で包括的に行える柔軟な制度です。
成年後見制度に比べて、
- 資産運用が可能
- 毎月の報告・報酬負担がない
- 契約内容を家族の実情に合わせて設計できる
というメリットがあります。
専門家のサポートは必要ですが、将来の安心を考えれば、コスト以上の効果があります。
一番大切なのは「お金の話」ではない
ここまで金融・法務の話をしてきましたが、
本当に大切なのは「家族で話し合うこと」です。
資産をどう守るかよりも、家族の信頼関係をどう守るかが先です。
お金の話を避けずに、オープンに話し合える家庭こそが、最も強い備えを持つ家庭だと思います。
今日からできる一歩を
口座凍結への対策は、「口座を一つにまとめる」「代理人制度を調べてみる」など、
小さな一歩から始めることが、将来の大きな安心につながります。
もしこの記事を読んでくださっている方が、私と同年代(30〜40代)で、
親の終活や老後の生活支援を考え始めている段階であれば、対話を始めてみるタイミングかもしれません。