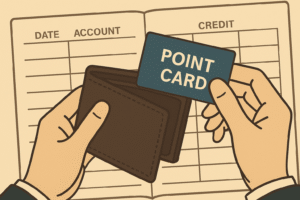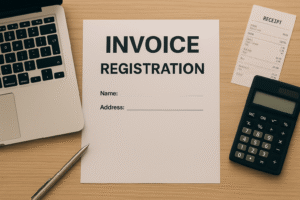不動産は「資産」か「費用」か?簿記3級の知識で考える持ち家と賃貸の違い
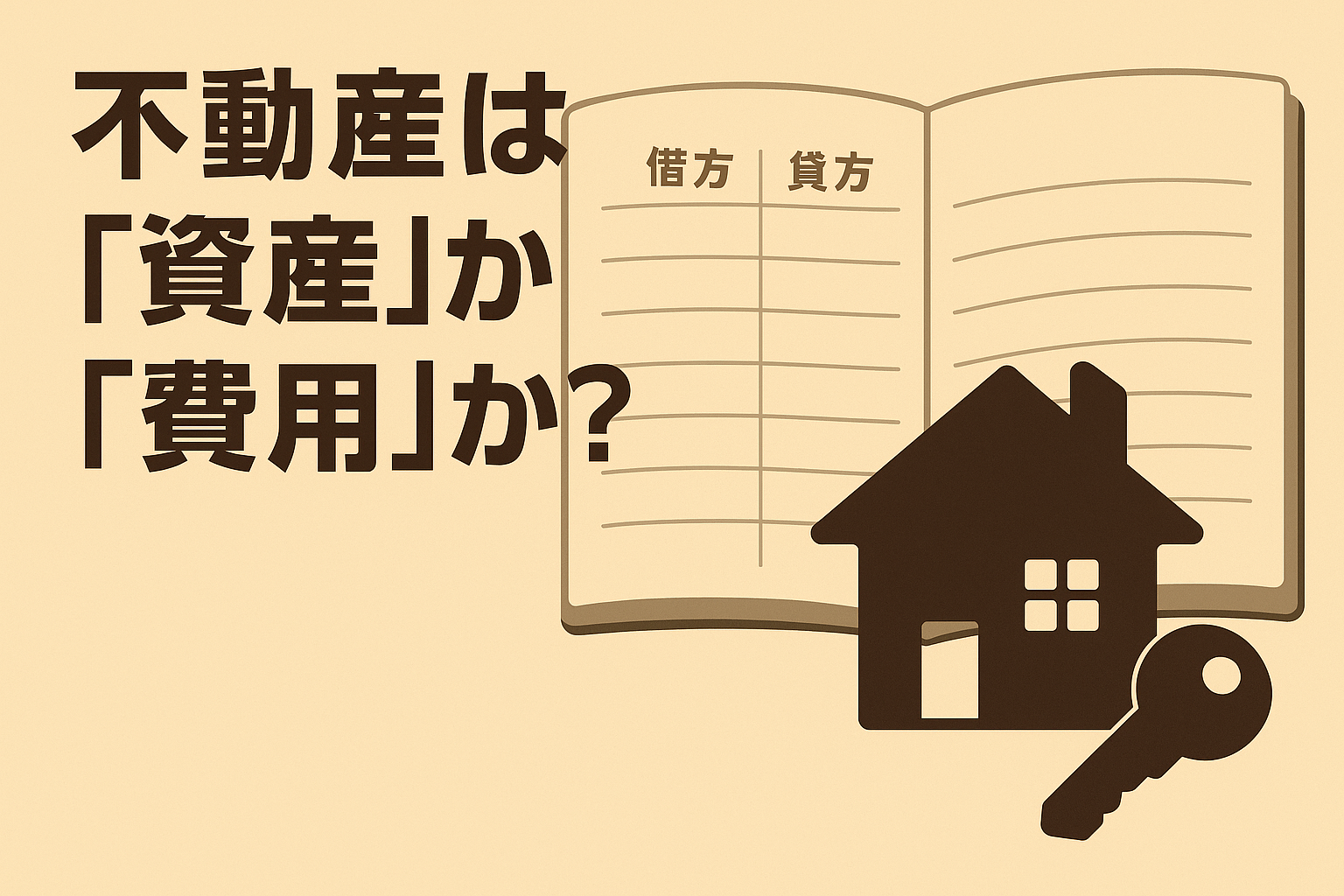
家を買うか、借りるか。
誰もが一度は考えるテーマです。
この論争を、簿記3級レベルの「仕訳の視点」で整理してみましょう。
どちらも一長一短ですが、会計的に見てみると、構造の違いが明確になります。
目次
賃貸は「費用」で終わる構造
賃貸住宅に住む場合、仕訳は非常にシンプルです。
(借方)地代家賃 100,000 / (貸方)普通預金 100,000
住んだ期間に応じて費用として消えていきます。
つまり、損益計算書(P/L)だけを通過し、貸借対照表(B/S)には残らないのが特徴です。
更新料を支払う場合も、いったん「権利金」として資産に計上してから、更新期間で償却します。
(借方)権利金 100,000 / (貸方)普通預金 100,000
(借方)支払家賃 4,000 / (貸方)権利金 4,000 (毎月償却)
しかし、結局のところ、最終的にはすべてP/L上の費用になります。
10年間、月10万円の家賃を払い続ければ、単純に1,200万円+更新料や退去費用。
支払った金額はすべて「消費」されたと考えられます。
持ち家は「資産」から始まり、費用を伴う構造
一方、住宅を購入する場合は、最初の仕訳からまったく違います。
たとえば、住宅ローンで5,000万円の家を買った場合(頭金500万円とすると):
(借方)建物 5,000万円 / (貸方)借入金 4,500万円
(貸方)普通預金 500万円
ここでは「建物」という資産がB/Sに登場します。
家賃のようにすぐ消える費用ではなく、長期的に使う「資産の取得」です。
住宅ローンの返済時はこうなります。
(借方)借入金 ××× / (貸方)普通預金 ×××
ただし、支払う中には「利息部分」もあり、それは費用になります。
(借方)支払利息 ××× / (貸方)普通預金 ×××
また、固定資産税・火災保険・修繕費も発生します。
(借方)固定資産税・保険料・修繕費 ××× / (貸方)普通預金 ×××
家計の簿記では「減価償却」はしない
事業用不動産なら、建物の取得価額を耐用年数にわたって費用化します(=減価償却)。
しかし、自宅(生活用資産)の場合、減価償却は会計上行いません。
つまり、帳簿上の建物価値は下がらなくても、実際の市場価値は減る可能性がある。
このズレが、賃貸との違いを見極める重要なポイントだと思います。
10年後にどうなるか?会計で比較する
仮に5,000万円で購入した家を、10年後に4,000万円で売却できたとします。
すると実質的な「費用」は、
1,000万円(値下がり分)+固定資産税や修繕費などの諸経費となります。
単純計算すれば、10年間で1,000万円+諸費用=1,200万円程度で住めたことになります。
もし近隣の賃貸相場が月10万円(10年で1,200万円)なら更新料や賃貸の初期費用を考えると、
購入の方が若干有利だったといえるでしょう。
簿記で見る「賃貸」と「購入」のちがい
| 観点 | 賃貸 | 購入 |
|---|---|---|
| 会計区分 | 費用(P/Lのみ) | 資産+費用(B/SとP/L両方) |
| 初期支出 | 敷金・礼金・仲介手数料など | 頭金・登記費用など |
| 維持費 | 家賃・更新料 | 固定資産税・修繕費・金利 |
| 資産性 | なし(消費) | あり(再売却可能) |
| 変動要素 | 低い(定額支出) | 高い(相場・金利・修繕) |
| リターン | なし | 売却益が出る可能性あり |
簿記の観点で見ると、賃貸はシンプルな費用構造、購入は複雑な投資構造です。
「どちらが得か?」ではなく、「どちらの変動リスクを取れるか?」という話になります。
税理士の視点:仕訳の数が語る「自由度」
仕訳の数で見ると、
賃貸は「家賃/預金」の1行で完結します。
一方、購入は「建物・借入金・利息・固定資産税・修繕費…」と多くの勘定科目を経由します。
つまり、マイホームは“変数が多い取引”です。
値上がり益を狙うなら投資性を伴うため、
「どんな物件を買うか」「どのタイミングで売るか」が損得を左右します。
なぜ売ることが前提なのかと思われるかもしれませんが、売却しないと最終的なマイホームの資産価値がわからないからです。
翻って、再販価値(リセール)が高い家を買えるなら、購入が有利になるケースが多いと考えます。
ちなみに私は、リセールが高い家を見つけて購入する自信が無いのでずっと賃貸派です。
まとめ
賃貸か購入かを「どっちがお得か」で決めると、答えは出ません。
でも、簿記で見ると構造がクリアになります。
- 賃貸:支出=消費(費用だけ)
- 購入:支出=投資+費用(資産性あり)
お金の流れを仕訳で理解すると、
感情ではなく構造で判断できるようになります。
もちろん、感情面を重視して判断されることを否定するつもりはありません。
もし、簿記3級を取得されていらっしゃるのであれば、ご自身の住まいを仕訳で考えてみても面白いかもしれません。
以上、簿記が日常に役立つ瞬間の第2弾をお送りいたしました。