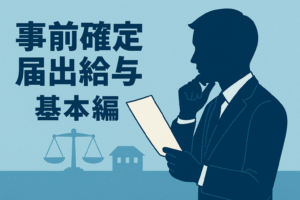事前確定届出給与:応用編
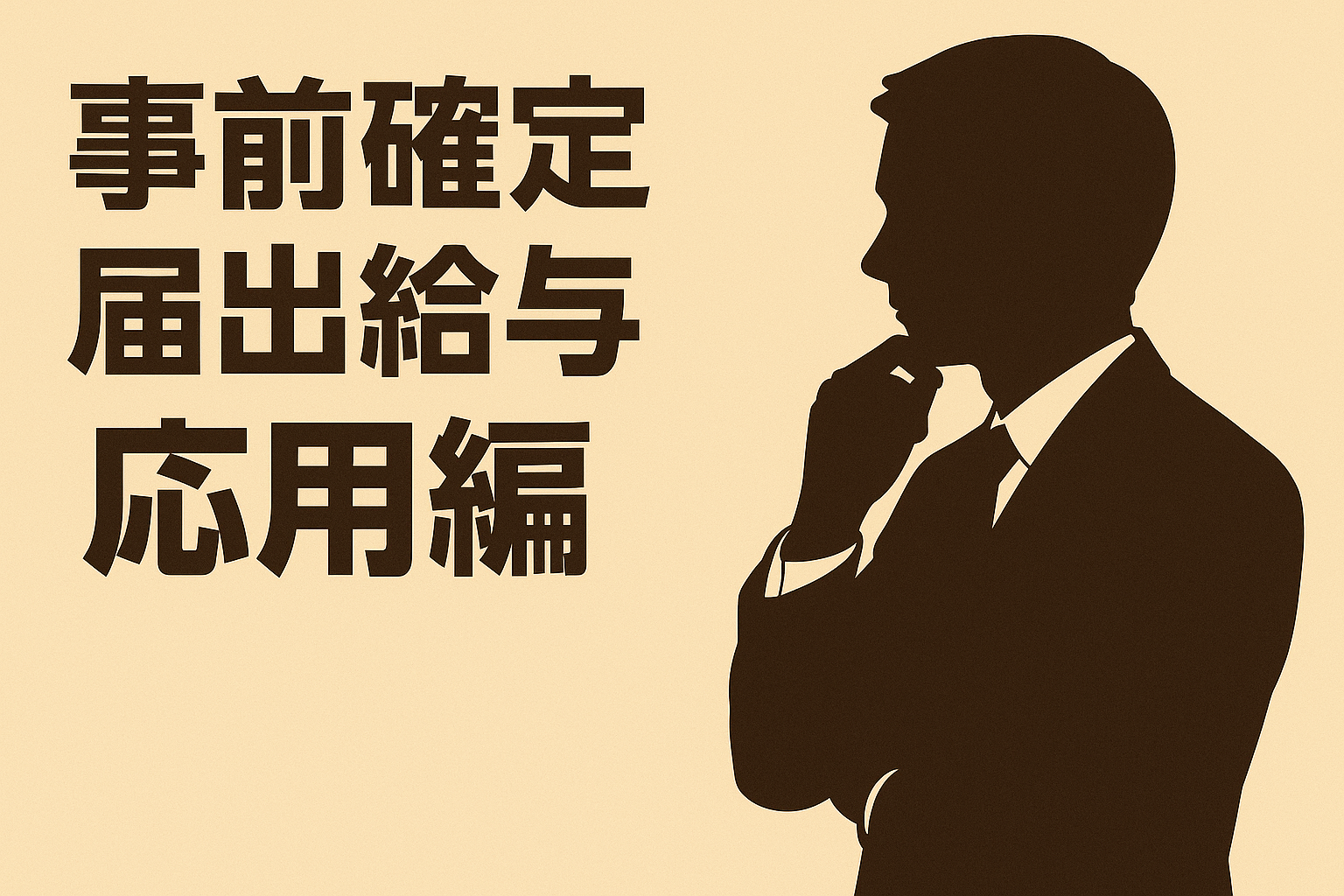
「事前確定届出給与の届出はしたけれど、実際の支給を見送った」。
あるいは「合同会社でもこの制度は使えるの?」。
今回は、そんな実務でよくある2つの疑問を取り上げます。
前回の「基本編」では制度の仕組みを整理しましたが、今回は応用論点です。
支給ゼロの場合の税務上の考え方と、合同会社における届出期限の扱いを解説します。
目次
支給ゼロでも「何も起きない」とは限らない
まずは、届出をしたのに支給しなかったケースです。
税務署の立場では「支給していないなら損金算入もされていない。
否認するものがないから問題なし」と考えがちです。
一見もっともらしい話ですが、それだけで完結しないのが実務です。
ここには、会社法と民法の理解が欠かせません。
支給決議をした時点で「債務」は発生している
定款や社員総会で支給を決議した時点で、会社には報酬債務が発生します。
その後に「不支給決議」を行う場合、この行為は債務の消滅にあたります。
つまり、支給していないとしても、報酬債務を免除(または放棄)した事実が残ります。
そのため、税務上は「債務消滅益」として課税対象となる可能性があります。
不支給決議をしていない場合
不支給決議をしなければ、会社には報酬債務が残ったままです。
この場合、支給対象者側に報酬債権が残るため、経済的利益の供与として支給するつもりだった者
に対する源泉所得税の課税関係に発展することもあります。
「支給ゼロ=何も起きない」とは限らないのです。
不支給決議をした場合
不支給決議を行った場合には、債務が消滅した事実が生じます。
ここで重要なのは、「支給しなかった」だけでは足りないという点です。
いつ・誰の同意で・どのように決議されたのかを記録しておく必要があります。
結果として支給がゼロでも、債務の扱い方を誤ると課税リスクにつながる可能性があります。
届出制度を使う際は、損金算入の可否だけでなく、債務の成立・消滅にも意識を向けるべきかと思います。
合同会社でも使える? 届出期限の考え方
次に、合同会社の業務執行社員に対して事前確定届出給与を支給する場合です。
株式会社とは仕組みが異なるため、届出期限の捉え方があいまいになりがちです。
最近、東京国税局がこの点について文書回答を出し、実務上の整理が明確になりました。
合同会社でも「役員賞与」として届出可能
法人税法上、合同会社の業務執行社員は「役員」に該当します。
したがって、株式会社と同様に事前確定届出給与を使うことが可能です。
具体的な流れは次のとおりです。
- 定時社員総会で、業務執行社員ごとの報酬・賞与を決定
- 「支給日・金額・対象者」を記載した届出書を作成
- 届出期限までに税務署へ提出
- 届出どおりの金額を届出どおりの日に支給
この流れを守れば、支給時に損金算入できます。
届出期限のルール
届出期限は、原則として決議日から1か月以内です。
ただし、決議日が「職務の執行開始日」より後の場合は、
開始日から1か月以内が期限になります。
株式会社では「職務の執行開始日」が明確ですが、合同会社では曖昧です。
そこで、東京国税局は次のように整理しました。
定時社員総会で報酬や賞与を決定する場合、
その総会日を「職務の執行開始日」とする見解で差し支えない。
つまり、届出期限は定時社員総会の開催日から1か月以内となります。
この整理により、合同会社でも安心して制度を活用できるようになりました。
文書回答の意義
この回答により、合同会社での届出期限の解釈が統一されました。
定時社員総会を職務開始日の基準とすれば、株式会社と同じスキームで運用できます。
さらに、合同会社でも事前確定届出給与を活用した税務戦略が可能になった点は実務的に大きな前進です。
決議・届出・支給を「決めたとおりに行う」ことが、制度を活かす最大のポイントです。
まとめ
事前確定届出給与は、単なる損金算入のテクニックではありません。
制度の理解と記録の整備を両輪で進めることで、初めて効果を発揮します。
支給ゼロでもリスクはゼロではない。
合同会社でも活用できる。
この2点を押さえるだけでも、経営判断の幅は大きく広がります。